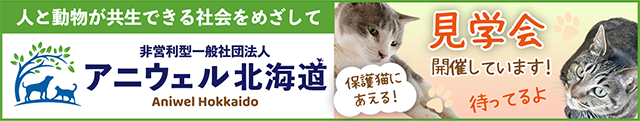秋も深まり、雪の便りが届きはじめていますね。毎日動物たちと過ごしていますが、飼主さんの中にはお子さんを連れてこられる方がいます。開業して19年、赤ちゃんだったお子さんが大人になりそして新しいペットたちを連れてこられるようになりました。
今回は子供と動物との関わりについて書こうと思います。25年ほど前からテレビゲームや玉子っちなどが出て来て、遊びが家の中にこもってできるものが多くなりました。「肌のあたたかさ」が伝わらない遊びが多くなり、「命」が軽々しく扱われ、仮想の「戦い」がくりひろげられ、「勝つ」ことが目的となり、負けたり、死んだら簡単に「リセットボタン」。しかし、現実は違います。人間や動物、学生時代よく細胞培養をやりましたが、一つ一つの細胞も「命のリセット」はできません。だからこそ「命」を大切に思うし、慈しみがわいてくるのです。
核家族化、高齢化社会、ストレスの多い競争社会において、大人たちだけでなく子供たちも否応無しにストレスを感じていると思います。「安らぎ」「孤独感の充足」「愛情を注ぐ対象」「ともに喜びを感じる」「きずな」「笑い」「会話」などを求めてペットを飼う方が増えています。しかし「生き物」ですから、楽しいことばかりではありません。
動物と子供の心の発達の関係が教育界で報告されています。動物に関心を持ち知識を得ることは「知るよろこび」「学ぶたのしさ」を知ることにつながり、動物と遊んだり、ならしたり訓練することは自分との一体感を得ることにつながり、「可愛い」「かわいそう」「すごい」と感じることは感情移入、他者への思いやり、感動につながるといわれています。 そして毎日の世話(食事、トイレ、散歩、掃除など)をすることで観察力、持続力、忍耐力を養い、より良い食事や快適環境を考えることで創意工夫、想像力が身に付くと言われています。ペット全体の行動を観察することで、自然への気づきが生まれる。他人に迷惑をかけないように心配ることで、社会のルール、責任感が身につくと言われています。
そして何よりもペットを通してかぞくの会話、笑顔が増え、ペットに対する大人の行動から子供たちはいろいろなことを学びます。いろいろな「いのち」が大切にされる社会になってほしいと思います。 これから寒くなりますので皆さん気をつけてください。