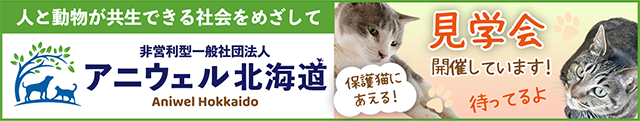いよいよグラコムの連載「ペット医療コラム」最後の投稿となります。いつもテーマを考えるのに時間がかかりますが、最後となると尚更です。
遠軽町の「北海道家庭学校」をご存知の方も多いかと思います。15年ほど前には「大地の詩〜留岡幸助物語」という映画も上映されました。その北海道家庭学校の玄関先に「流汗悟道」と書かれた石碑があります。人間は共に汗を流して、初めて分かることがあると解釈しています。また、ホームページには続けて「多くの人々の世話になっていること、助けを受けていること等々、自ら汗を流して体験しなければ、何も分からないのです。」とも説明されています。私がこの「流汗悟道」を知ったのは本コラム第199回でも紹介した山根義久先生の希望で家庭学校を案内した時でした。それ以来大切にしている言葉です。
世の中に生まれて宝物の名前を付けてもらい、愛情を注がれて大きくなっていく子供達。子育ては大変ですが、笑顔、寝顔を見ると癒され、慈しみが生まれ、親たちも成長していきます。子供達も地域の人たちから声をかけられ、同世代の子達と汗をかくほど遊び、喜怒哀楽を自然と身につけ、感性が目覚めていきます。「三つ子の魂 百まで」と言われていますが、この時期に感性を芽生えさせる子育て、教育を行わないと思春期の頃、問題行動を起こすとも言われています。戦後80年の日本を振り返ると少々「知性」を追い求めすぎたかもしれません。以前「道徳」という教科がありましたが今は「特別の教科 道徳」となり、改めて「感性」を育むことが見直されているようです。「感性」を育むために「本」との出会いも大切です。初めは親から抑揚を混えて絵本を読んでもらい、場面によっては親に抱きしめられこともあるでしょう。そして保育園などでは、絵本、紙芝居を同じ空間で体験していきます。あの時の子供達の生き生きとした眼はすごいですよね。さらに昔話などを読んだり童謡を聞くことで「感性」が育まれる一助になるかと思います。
獣医師として42年間動物に関わってきて、あらためて動物たちが人にもたらしてくれる恩恵・プレゼントの多さと大きさ、そして深さを感じています。可能であれば、脳細胞が急速に増え、細胞内ネットワークが構築される3歳までに動物と一緒の環境を作っていただきたいと思っています。私は農家出身ですから生まれた時から動物たちに囲まれて育ってきました。柔らかくて温かい被毛、たくさんのことを伝えようとする瞳としっぽ。頼り頼られる存在。時には生と死にも向かい合ってきました。「命」が生活の場に存在することって素晴らしいと思います。犬や猫はいつまでも人の年齢で言えば3歳とも言われています。「相棒」と生活することにより、心と身体の抵抗力もつくことでしょう。親からの抱擁、絵本や童謡との出会い、そして何万年も前から人と共に生活し安全とされているペットがいる環境で感性豊かに育って欲しいと思います。
日本のペットの飼育頭数は犬は減少、猫は横ばいが続いています。ペットの購入価格の高騰、経済的問題、核家族化、少子高齢化社会、新型コロナ感染症の影響など様々な要因が考えられます。そんな中でも人間の都合で飼育放棄されたペットたちは増加し、社会問題化してきています。数年前から縁あって動物愛護活動に携わるようになりました。そして多くの方々と知り合い、解決困難と言われてきた案件にも微力ながら携わるようになりました。「流汗悟道」これからも大切にしたい言葉です。
200回も連載してくれたグラコムさんにも感謝して筆をおきます。ありがとうございました。