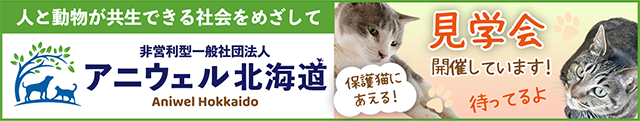3月に入り、春の兆しを感じる頃となりました。
年度末となり何かとお忙しい毎日を迎えていると思われます。
11日に大震災の日を迎えますが、決して忘れないようにしていきたいと思います。
今回も麻酔のことを書きたいと思います。特に肥満が麻酔におよぼす影響についてお伝えします。
肥満とはいろいろ定義がありますが、「過剰な脂肪の蓄積により、さまざまな臓器機能や健康状態、そして日常生活に支障をきたす状態」をいいます。
そして、肥満であること自体が体に影響を与えます。
まずは呼吸への影響について。
胸壁の周りに厚い脂肪が付着しているため肺が膨らみにくく、胸の弾力性が低下しています。
また、お腹の臓器も重くなり、呼吸の際の横隔膜の動きも悪くなります。
そのために換気状態や換気能力が著しく低下し、酸素が体に取り込まれにくくなっています。
それにより普段でも呼吸数が多く、少し動いただけでも呼吸が荒くなってしまいます。
次に循環器への影響について。
体重が増加すると、それに伴って必要とする循環血液量が増えます。
心臓から送り出す血液量(心拍出量)を維持するために、心拍数を増やして対応しています。
つまりは、日常的に心臓に余分な負担を与え続けていることとなります。
その他、膵炎や糖尿病、脂肪肝、甲状腺機能低下症、変性性関節炎などの関節異常、椎間板ヘルニアや変形性脊椎症などの背骨の異常などが肥満によって生じる病態として認められています。
さて、このような動物に様々な処置・手術を施すために、麻酔をかけなくてはならないことがあります。
先月も言いましたが、「気道の確保」と「換気」、そして「血液循環」が麻酔の命を守る3要素です。
肥満の動物は口の中までも狭くなっており、気道も脂肪で押されていますので、気道の確保についてもハンディがあります。
ということは命を守る3要素とも、麻酔をかける前から十分ではないことがご理解いただけると思います。
また、多くの麻酔に関わる薬は体重計算で量を決めますが、肥満の動物の場合、そのままの体重で投与すると過剰投与となってしまいます。
さらに多くの薬は脂肪に溶けやすいため体中の脂肪に吸収分布されてしまいますが、脂肪組織には血流が乏しいため代謝が非常に遅いという特徴があり、麻酔から醒めるのが遅くなります。
このように、肥満動物への麻酔は“麻酔をかける前"も“麻酔中"も“麻酔後"も、とても神経質になってしまいます。
獣医医療サイドとしては無事に終わるように最善を尽くしますが、飼主さんも動物が肥満にならないようにしていただきたいと思います。
動物は自ら食事を用意しません。食事・おやつを与えているのは飼主さんです。
なかには病気で太る場合もありますので、獣医師・動物看護師に相談してみて下さい。