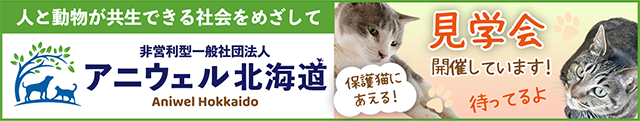4月に入り新年度を迎えましたが、新たな気持ちでスタートを切ったところだと思います。
また、東日本大震災と原発事故の復旧が進むことを願っています。
雪解けが進むと、オホーツク地方はすぐマダニたちが活動をはじめます。
犬や猫が散歩で近づいてきてくれるのを待ち構えています。
早めのマダニ予防を動物病院で相談されるといいでしょう。
麻酔シリーズの最後は、手術に伴う「痛み」について書きます。
古い話をして申し訳ありませんが、開業当初(20数年前)は「痛みの管理」という考えはあまり一般的ではありませんでした。
「動物は痛みに対して強いから、鎮痛など必要ない」とか「痛みがあった方が手術の後おとなしくていい」とか、「傷口をなめなくていい」とか言われていたのが事実です。
確かに「痛み」を感じることは生体防御的には必要なことです。
お腹を開けたり、骨折を修復したりする手術のあと「痛み」を感じるのは数時間から数日と言われていますが、これだけ長く痛みを感じると生体防御が過度に働き、体に悪影響をおよぼしてきます。
手術の種類や個体差のありますが、呼吸機能の低下、交感神経刺激による脈拍の増加、血圧上昇、胃腸の運動低下による吐き気、腎機能低下、カテコラミンが多く出過ぎぎることによる代謝亢進などがおこります。
また、精神的にも不安や恐怖をおぼえ、術後の回復を遅らせるばかりではなく、人間不信や病院大嫌いになってしまいます。
これらは決していいことではなく、手術の影響からの回復を妨げるものであり、可能な限り「鎮痛:痛みを和らげる管理」をしてあげることが大切になってきてます。
ではどうやって痛みを管理すればいいのでしょう。
「痛み」は手術による侵害刺激(切ったり、臓器を持ち上げたりする刺激)が脊髄神経に入り伝達され、その刺激を大脳が「痛みの感覚」として感じることで成立します。
この感覚を抑制するために麻酔薬を使うわけですが、一般的な麻酔薬は痛みの刺激を運ぶこと(伝達)を阻止することができません。
そのため麻酔薬だけでは十分ではなく、手術中や術後に「痛い」と感じてしまうことになります。
そのため、鎮痛剤の併用が必ず必要になります。
その使用にあたっては「周術期疼痛管理」といって、手術中だけでなく、手術前~手術中~手術後の痛みのことを考えていきます。
鎮痛薬も効果と安全性が認められたものを目的にあわせて使用します。
鎮痛薬を使うと手術後の醒め方が穏やかです。
また、不安や恐怖もさほど感じないためか、抜糸に来たときもあまり嫌われないで済みます。
獣医師は予測される痛みを飼い主さんにお話すると思いますので、鎮痛剤の使用を勧められたときは是非使ってあげて下さい。