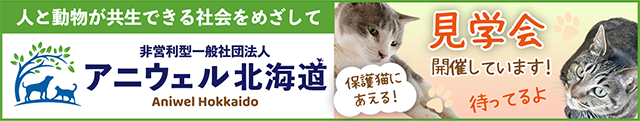11月になりましたが、ちゃんと冬は来るものですね。
急に寒くなり体調を崩されている方が多いようです。皆さん気をつけてください。
先月、旭川で「獣医再生医療の夜明け」というお題の講習会を聞いてきました。
山中教授がiPS細胞の研究でノーベル賞を受賞し、脚光をあびている再生医療の話だったので興味深く聞いてきました。
今回は胸水について書きます。胸水とは胸腔にたまった液体のことです。
正常でもお湿り程度にはありますが、異常に溜まった状態になると肺が膨らむスペースが減少して呼吸困難になってしまいます。
重篤な場合は、適切な処置を早急に行わなければ死亡する場合もあります。
呼吸の異常に早く気づくことが大切です。
まず、安静時や寝ているときでも呼吸数が増加します。
胸水の量が多くなってくると、パンティング(喘ぎ呼吸)や犬座呼吸(おすわりの姿勢のまま動けない)になってきます。
こうなったら興奮させたり、無理に動かすだけでも呼吸が止まる場合もあります。 この状態で病院に来られることもありますが、あまり動かせないので、まずは酸素の部屋に入れて様子をみることしかできません。
少し落ち着いたらレントゲンを撮ります。
胸水が溜まっていることが確認されたら、興奮しないように細心の注意を払いながら、胸水を抜く処置をします。
場合によっては1リットルも抜けることがあります。
この処置が無事に終わると、動物たちが「おかげで楽になったよ」と眼で答えてくれます。
こんなときはうれしいですね。
しかし、胸水を抜いただけではまだ治療のスタートを切っただけです。
胸水貯留の原因を追求しなければなりません。
胸水の色もいろいろで、赤ければ出血があるかも、黄色くて臭いがあれば化膿や炎症があるかも、白ければリンパ管の異常があり乳糜胸になっているかもと想像します。
さらに、タンパク量や細胞を顕微鏡で観て診断を進めていきます。
原因は胸の中にあることがほとんどで、外傷、腫瘍、胸膜炎、肺葉捻転、うっ血性心不全などがあります。
また、胸以外の原因でも胸水が溜まることがあります。
血液中のタンパクが異常に少なくなる低タンパク血症や、血液凝固不全症などです。
原因が分かると、それぞれに対する治療を開始します。
場合によっては手術が必要です。
また、症状が安定するまでは胸水が再度溜まってきますので、胸腔に管を入れ何回も胸水を抜く必要があります。
何れにしても、動物も飼主さんも大変です。
早期発見で早く楽にしてあげたいものです。
日頃の観察をお願いしますね。
PS.第4回北見マラソン走りました。関係者の皆様、応援の方々、そして参加した皆さんありがとうございました。