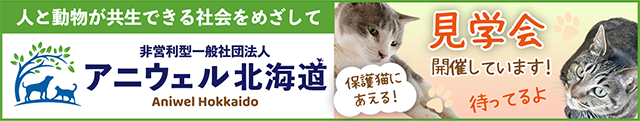師走を迎え、忙しい毎日かと思います。冬支度はもう終わりましたか? ペットたちも気温の低下や日照時間の変化を感じ、冬支度を始めています。寒さから身を守るため毛足が長くなり、柔らかいアンダーコートも増え、見た目にもふっくらとなります。また暖をとるのもうまくなり行動も変わってきます。暖かい場所を探すのは天才ですね。日当りの良い場所、ストーブの前、こたつの中、床暖の上など。時間帯によって移動しているのも分かります。快適な場所を探すのがうまいですね。
暖かい季節には症状が出ていなくても、冬になって初めて、症状が出てくることもよくあります。一般的に、泌尿器や呼吸器、関節や運動器の病気が冬に多くなるといわれています。まず、泌尿器の病気について説明します。寒くなってくると散歩に出かける回数も減り、動かないので喉も乾きづらく、水を飲む量が極端に減ります。飲水量が減ると尿量が減るため、尿石症や膀胱炎を起こし、血尿や頻尿になりやすくなります。予防のためにお水をよく飲ませるように心がけてください。あまり飲まない場合は、味付けしていない肉の煮汁などを混ぜてもよいかもしれません。尿の回数や時間、色に変化が出てきたら要注意です。次は呼吸器の病気です。冷たい外気や暖房で乾燥した空気によって、喉の粘膜が弱くなり、風邪をひいてくしゃみやせきをしやすくなります。定期的な換気や加湿を心がけてください。特に寒さに弱いチワワは要注意です。猫もこの時期ヘルペスウィルス感染症やカリシウィルス感染症が流行ってきます。ワクチン未接種の場合はうたれることをお奨めします。次に関節や運動器の病気ですが、冬に多くなるのは、寒いと体の血行も悪くなるからです。関節が温まっていない状態でいきなり走ったりしたら危険です。例えば朝まだ寒い時間帯でも、イヌやネコちゃんはボール遊びをすると反射的に動きますが、まだ関節が温まっていないため、関節を痛めることがあります。前十字靭帯断裂ということもあります。特に高齢犬や太り気味の子は注意が必要です。
室内犬が増えて、冬でも北海道の室内は暖かくなってきていますが、それでも他の季節に比べますと寒いです。ウオーミングアップになるような軽い運動をしてから遊ぶのが良いでしょう。飼主さんも寒いとついつい散歩も行きづらくなってきますが、ご自身の運動のためにも散歩に出かけてほしいです。そして帰ってきたら、十分なお水を用意してください。また、ペットはちょっとした体調の変化を言葉で伝えることができません。ある日突然、元気がなかったり、食欲がなくなったと気付くことも多いのです。ちょっとした体調の変化に気付くために、ヒト以上に定期的な健康診断が大切です。中高齢のペットは年に2回の健康診断が推奨されます。ぜひ大切なご家族のために早期発見、早期治療を心がけてくださいね。そして良い年を迎えてください。