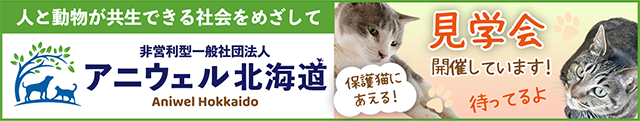学生時代(20年以上前)は寮生だったため、先輩、友人、後輩と「酒の一滴は血の一滴」と言いながらよく盃を傾けたものです。楽しかったなあ…話が変なスタートとなりましたが、1滴は約0.05cc、2滴なら0.1cc。この0.1ccの血液から分かることをガンのことに関連づけてお話します。
病院に来られる動物たちは体重が30gから80kgとさまざまで、なおかつ元気がなく血圧が下がっている子が多いですから、精一杯がんばっても0.1ccしか血が取れないことはよくあります。この血から最大限の情報を得ようとし優先順位をつけながら検査を進めます。
白血球、赤血球、血小板の数、赤血球の酸素を運ぶ能力の目安、肝臓の酵素2種類(GOT、GPT)、黄疸の目安(ビリルビン)、腎臓(BUN)、血糖値、コレステロール、タンパク量、そして血液を染色して顕微鏡検査。ここまでは検査できます。顕微鏡でみた血液(血液塗沫と言います)は別世界です。染色してあるので赤や青の濃淡で色付けされていますが、とてもきれいな世界です。時間が許せばいつまでも見ていたい気持ちです。
この塗沫にはすごい情報があります。白血球には様々な種類があるのですが、このバランスの異常、白血球の顔の変化などで白血病やカラダのどこかに起きている腫瘍関連を含めた炎症、中毒性の変化、ホルモンの異常を発見することができます。
赤血球をみると元気なもの、色白なもの、今にも壊れそうなもの、赤血球同士手をつないでいるもの、寄生虫に侵されているものなどいろんな顔を見せてくれます。
貧血、中毒、免疫疾患、寄生虫病などの診断の助けになります。腫瘍の場合は多くの場合貧血があります。血小板は多いと血小板性の白血病なども疑いますが、大部分は少ないことが問題となります。血小板は出血があればそれを止めるのに重要な役割がありますが、少ない場合はどこかに出血があるとか、壊されているか、作られていないかということになります。
出血を伴うガンも多いです。ガンの種類や程度を考えるのに顕微鏡の世界は多くを語ってくれます。
わずか2滴の血液で動物のおかれている状況の目安をつけることができます。あとは飼主さんから伺ったお話や実際に動物を触ったり、見たり、聞いたり、そして嗅いだりしながら、おおかたの診断をつけていきます。「血の1滴は…」ではありませんが、動物にとっても私たちにとっても大切な血の1滴です。