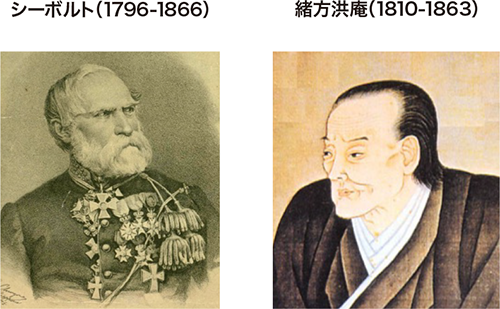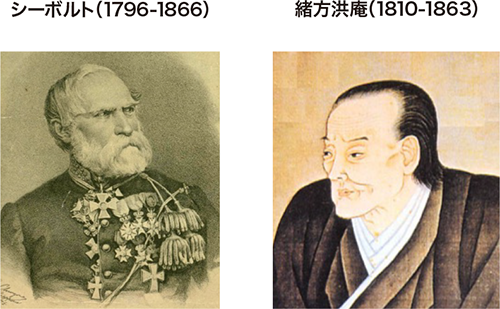日本の医学史
今回は、医学の歴史(日本の医学史)ついてお話しします。
日本の医療は、祈祷から始まり、どのように現代医学と進化したのでしょうか。
飛鳥時代
8世紀に入り、律令国家の歩みを始めた日本は、医療を担当する「典薬寮」を設け、医生は、渡来人による指導を受け、中国の医書を学び、医術を習得していきました。
鎌倉時代~室町時代
官医に代わって活躍するようになったのが僧医です。室町時代に入ると、歯科や眼科、産婦人科など、専門分野が細分化され、それぞれの専門家が流派を開くようになりました。また、応仁の乱以降は、戦場に同行して刀傷を治す金創医(外科医)も現れました。
江戸時代
8代将軍徳川吉宗は1722年、小石川薬園の中に小石川養成所を創設。貧しい病人や身寄りのない病人を収容。また、幕府の医学校である医学館は、1791年に、多紀 元簡の医学所・躋寿館(せいじゅかん)を接収。漢方医学の中央教育機関として、江戸時代末期まで存続。
1774年に杉田玄白らが『解体新書』を出版すると、西洋医学は急速な広がりを見せました。緒方洪庵の「適塾」や佐藤奉然の「順天堂」など、各地に蘭方医学塾が開かれました。
長崎ではドイツ人医師のシーボルトが日本人医師に西洋医学を教えました。また、漢方医でありオランダ医学も学んだ華岡青洲が、世界初の麻酔手術を成功させるなど、漢方とオランダ医学の融合も進んだ時代でした。1858年に漢方医により江戸に作られた種痘所は、医師の養成も行っており、後に幕府直轄の医学所となり、幕府は漢方の医学館と合わせて、漢方と蘭方の両方の医師養成施設を持つようになりました。後の東京大学医学部です。 明治・大正・戦前の医療
明治政府は、医療の近代化を目指し、西洋医学に基づく医学教育と医師開業免許制度を定めた「医制」を実施。医師は西洋医学を学び、国家試験に合格した者のみが成れるようになりました。1938年に厚生省が設立、国民健康保険が導入。国家医療体制の下、全国に大学医学部が開設されました。
戦後の医療
戦後、日本は米国を手本に医療制度の改革を行い、民主主義の精神に基づき、医療は社会保障の意味合いを強く持つようになりました。
近年、医療費が国の財政を圧迫するようになった為、医療は「治療から予防へ」と方向転換が図られています。生活習慣病の予防や、病気の早期発見に重点が置かれるようになりました。
次回は、『循環器内科の歴史(その1)』についてお話ししたいと思います。